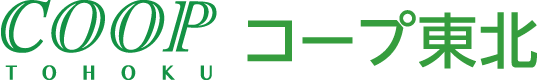商品検査の取り組み
微生物検査
生協が取り扱っている食品は、原料や製造工程などの情報を取引先からいただいています。それをもとに、微生物の影響を受けやすい食品群を選んで検査を行い、安全性を確認しています。検査の結果は、店舗やメーカーでの衛生改善に活用しています。
検査している項目
細菌の汚染状況を客観的に評価するための指標となる菌(一般生菌数、大腸菌群、大腸菌E.coli)。
人体被害や食品を変敗させる恐れがある菌(黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ、セレウス、乳酸菌、カビ、酵母、腸管出血性大腸菌(O157など))については、検査する食品群に応じて実施しています。
-

①サンプリング
食品は一定量を計り試薬を入れ試料液を作ります。
-

②スパイラルプレーター
この機械で試料液を寒天増地に塗ります。
-

③インキュべーター
一定の温度で培養し細菌を増やします。
-

④計測
培養された細菌の集落(コロニー)を数えます。
こんな検査をしています
1.商品を販売する前に検査し安全を確認しています
宅配商品の新規取り扱いが決まったら、腐敗・変敗しやすい商品や加熱しないでそのまま食べるなど「微生物の影響を受けやすい食品群」であれば、事前に検査を行なって商品が衛生的に管理されていることを確認します。
「微生物の影響を受けやすい食品群」の例 :弁当、米飯、冷惣菜、等。
2.継続して販売している商品は定期的に検査しています
取扱い中の商品も「微生物の影響を受けやすい食品群」であれば、定期的に検査して衛生的に管理されていることを確認しています。
3.お申し出があった商品は必要に応じて検査しています
組合員からのお申し出で、原因に微生物の影響が疑われるものについて、衛生状態の指標となる菌(一般生菌数や大腸菌群)や、食中毒菌の検査を行って問題が無いか確認をしています。
4.COOP商品(検査は日本生協連商品検査センターで実施しています)
コープ商品は、開発時の原材料や試作品、初回生産品での検査を実施して、商品が定められた基準を満たし、あるべき品質を維持していることを確認しています。
食中毒の病因物質の9割が微生物です。
食品の微生物検査は、食品の製造・流通過程において安全性確保がされていることの検証の一つで、万が一の人体危害を未然に防ぐことにつながります。
また、食品の腐敗・変敗等の多くは微生物の関与によるもので、製品の微生物検査により、製造工場や店内加工場の衛生管理状況を検証することで、食中毒の防止につながります。
微生物検査は食品の品質確保に有効であるのみならず、お申し出に対する迅速対応の基礎資料ともなりえるもので、継続的な検査実施が必要と考えています。
検査の実施状況